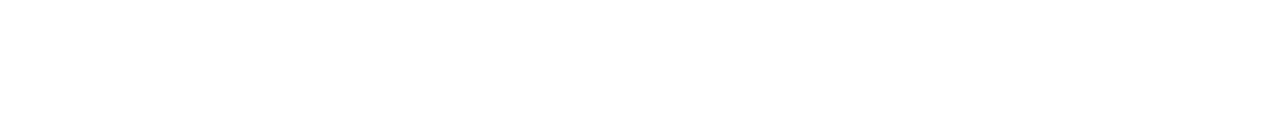
〜人生を「こんなはずでは」で終わらせないために〜
私は普段、緩和ケア医師として働いています。医師になって30年あまり、多くの患者さんと出会い、お別れしてきました。私のまわりの医療従事者・介護従事者などの人たちも、本当に熱心に、命の残りが短くなった人たちの「困ること」が少しでも少なくなるように、「良かった」と思えることが少しでも多くなるように、実に上手に患者さんやご家族と接しています。
しかし患者さんを看取った後に「こうすれば良かった」「もう少し時間があればもっといい看取りができたのではないか」と思うことは数知れず、「頑張れるだけ頑張ったんだからこれで良しとしよう」とは思えないこともしばしばです。ではこの上、何をどうすればいいのでしょう。
看取りが近い現場での工夫は、この「日本死の臨床研究会」ではたくさん取り上げられて議論が重ねられ、現場でも活かされています。しかし医療現場に至る以前の「日常」の中に、もう少し「命の残り時間の過ごし方を考える」ことを取り戻した方が良いのではないかと考えます。
死ぬことなどははるか未来の遠い話と思う日常の中で、また、つい死を遠ざけてしまいがちな高齢者の生活の場の中で、さらには災害や急病など突然の変化に飲み込まれた「非日常的な時間の経過」の中などで、現状よりももう少し死と日常の距離を近づけ、死について生について話し合いやすい日常にしていくことが、死の臨床の現場での負担を軽くして、より良い看取りを増やすことにつながるのではないかと考え、今回の大会テーマを「死と日常の距離感」としました。
日常の中で死について考える人は、少なくはないと思います。ただし多くもない。多くの人の日常の中で、丁度良い距離感で死と向き合い、必要な準備の中で今からでもできることはしておくようにすることが、不幸な死や残念な死を減らしていく結果につながると考えています。
第29回日本死の臨床研究会関東甲信越支部大会大会長 平方 眞